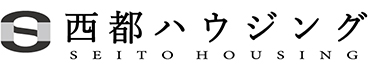相続対策サポート
- TOP
- 相続対策サポート
争族になりやすい不動産相続
円満相続のための対策をご提案します
相続財産に不動産が1つしかないケースでは「財産の分割」で揉めやすく、逆に不動産が多くあると「相続税の納税」において問題が生じやすくなります。
当社ではこのようなトラブルを回避するための最適な対策をご提案します。
こんなお悩みありませんか?

- 遺産分割で家族がもめないか心配
- 不動産をどのように相続すべきか
- 相続税で財産が減ってしまうのでは
- 不動産の評価額や節税方法を知りたい
- 認知症に備えた対策を検討したい
- まずは誰に相談すべきだろうか
サービスの特徴1
相続対策専門士がサポート

相続財産には不動産が含まれることが多くあるため、 相続トラブルを回避するためには不動産の専門知識が必要不可欠です。 当社では 「公認 不動産コンサルティングマスター相続対策専門士」 がお客様のパートナーとなり、 円満相続のための最適な対策とサポートをご提供します。
サービスの特徴2
ひとつの窓口で安心のサポート

相続対策には税理士や司法書士など様々な専門家が携わります。 私たちは相続対策のまとめ役として各分野の専門家と連携し、 お客様が混乱することがないよう、 ひとつの窓口で全ての相続手続きを行うようにしています。
サービスの特徴3
オンラインでの相談サポート

お住まいの場所から遠く離れた不動産を相続されるケースは少なくありません。当社では遠方にお住まいのお客様にはオンラインでのご相談を受け付けています。電話やメールだけでなく対面でのご相談ができますのでご安心ください。
STEP01
- 個別相談
- お客様からのヒアリングと相続対策のご説明をします
STEP02
- 資産分析
- 相続の対象となる資産の分析を行います
STEP03
- 相続対策のご提案
- 相続対策のプランを作成し、お客様と相続の方向性を決めていきます
STEP04
- 専門家のご紹介
- 必要に応じて各分野の専門家をご紹介します
STEP05
- 資産整理
- 相続対策にもとづいて資産整理を行います
STEP06
- 遺言書作成
- お客様のご意向通りに相続が行われるように遺言書を作成します
STEP07
- 相続手続きサポート
- 相続発生後の手続きが円滑に行われるようにサポートします
- Q相続が発生した場合、相続人には誰がなりますか?
- Q相続人が亡くなっている場合はどうなりますか?
- Q内縁の妻は相続人になりますか?
- Q再婚相手の子や内縁の妻の子は相続人になりますか?
- Q相続人が誰もいない場合はどうなりますか?
- Q相続の権利を失うことはありますか?
- Q法定相続分とは何ですか?
- Q相続人のなかで私だけが生前に贈与を受けていた場合はどうなりますか?
- Q親の介護をしていた相続人は相応の財産を相続できますか?
- Q相続放棄とは何ですか?
- Q遺産分割協議はどのような場合に必要ですか?
- Q遺留分とは何ですか?
- Q相続対策はいつから始めるといいですか?